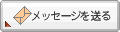2009年03月22日
日本百名居酒屋
日本百名居酒屋という番組をご存じでしょうか。


日本百名居酒屋という番組をご存じでしょうか。
旅チャンネルというところで放映していて、テレビ東京系でも流しているようなのですが、ヒゲのおじさんが各地の居酒屋で酒を飲んでいる所を放映するという、さすがに最初はちょっと戸惑う番組です。
この番組、実は「日本居酒屋紀行」を受けてもう10年以上も続く名企画で、最初は居酒屋でよく見かけるような酒呑みかとも思われたこのおじさんも、太田和彦さんという、後に述べますがなかなかの人物なのです。
本来は、日本全国、津々浦々の優れた居酒屋を訪問するという企画で、最初にこの番組を見た時は、確か東京の下町の飲み屋だったのですが、それはありがちな飲み屋で、そこでおじさんが飲み食いをして、夜の街に紛れ込むように去って行くという、正直なところ???な印象をどうにもできない番組だったのでした。
太田和彦さん
この番組の案内役で、企画者でもあるひげのおじさんは、太田和彦さんという本来はグラフィックデザイナーで、ネットの経歴では北京生まれ。当初は資生堂に入社して腕をふるっていたようです。最初は見知らぬ酒呑みのおじさんだったのですが、「居酒屋研究会」というものも主宰しているらしく、実はあの新潮文庫に居酒屋関連の著書が5本もあったのです。
そこで、そのうちの「超・居酒屋入門」を読んでみると、これがまたいいのです。文章に骨があって、なんともいえない味があって、しかも衒ったところのない文章は、かつて新潮文庫で野田知祐を初めて読んだ時の記憶をうっすらと思い出させるものがありました。
この本によれば、居酒屋とは「居心地を愉しむ」ところであり、街中で提供されるプライベートな空間、それは例えばヨーロッパのカフェやバールのような、気軽に入れて干渉されない場所なのですが、それが日本では居酒屋なのだということのようです。そこで、日本の中高年が、職場からも家庭からも距離を置いて、一人の個人に立ち帰る、そんな場所なのだということのようなのです。
まあ、日本では、近所のおじさんがいつでもぶらりと入って居座れるほど、喫茶店の文化が根付かなかったし、それに薄くて高いコーヒーなんか飲むなら、おいしい肴で酒でも飲みましょうということなのでしょう。
地域に根付いた名店
さて、そういう予備知識をもってこの番組を見直すと、実はなかなか味のある番組です。
まず、登場する居酒屋がとても貴重な店だったりします。
例えば、釧路の歴史のある炉端焼き屋さんなどは、建物そのものが持つ燻し銀の迫力に鬼気迫るものすらあるのですが、その炉端で、店を守り続けてきた老婆がいそいそと立働く姿。そして別の店では、既にすっかりモノトーンとなってしまった店内で、物静かな割烹着の女将さんがカウンターの片隅で手を休めてくつろぐ時、それがまるで夢二の構図そのもののようなものになっている時の、眩暈がしそうなアナクロニズム。これなんかは、すでに記録映像です。
料亭などのように決してお金をかけたわけではない建物が、まさに地元に親しまれたが故に歴史とともに受け継がれてきた、そんな味のある店。しかもなかなか行く機会のない地方の、知らなければなかなかブラリとは入りにくいお店が、映像としてたくさん残されています。
たとえば、まずYouTubeにある「会津若松篇」です。
会津若松篇1
会津若松篇2
会津若松篇3
主題と変奏
さりとて、これは居酒屋の紹介番組です。薀蓄のある厳選された食材を使って名料理人が華麗な腕をふるう、そんな見せ場はありえません。また名物店主の華麗なトークも期待できませんし、むしろこれは番組の空気をぶち壊すリスクの方が高いでしょう。
すると、番組の構成としては、注文して、呑んで、食べるだけという単調なものとならざるをえず、実際に過去の映像を見ても、このスタイルは本人も言っているように「10年前から代りばえのしない、いやまったく同じことをやっていると言ってもいい」ものになっているのです。
しかし、何回か放送を見ていると、そこにはある種の様式美としてのいくつかの見せ場があり、さらにそこにはいくつかのバリエーションがあることに気付きます。
「冷え方が最高!」
この番組では、何といってもまず一杯、何かで咽喉を潤してから料理を注文するというのがスタイルのようです。太田さんもかなりのビール党であるらしく、最初はビールから始まるパターンが多いようです。
そこでテーブルに届けられた生ビールのジョッキに手を伸ばし、最初の一口でそのままジョッキの1/3から半分くらいまで飲んでしまうのですが、ここでふと、時間が止まります。
太田さんの目が一瞬虚空を泳ぎ、明らかに冥界まで往復してしまっているのがわかります。
絶妙な間をおいて目に正気を取り戻すと、一言、
「うまい。」
この番組の最初の見せ場は、まずここです。
ここで生ビールを置いていない店だった場合には、もちろん瓶ビールになります。
しかし太田さん、著書を見ると、ビールの注ぎ方・泡の分量には一家言あるらしく、そのあたりの機微を知らない他人にビールを注がれるのは、実は嫌らしい。しかし、これはTVの取材です。そんな事情を知らない女将さんとしては、最初の一杯ぐらいはしっかりお酌するのが義務です。物静かにジェントルに呑むことを身上とした太田さんとしては、たとえ内心では最初の一杯が台無しになったとしても、番組の初っ端ですから何もコメントしないわけにもいかないのでしょう。この時、生ジョッキで冥界に遊んだときとは打ってかわって、すでに今の残念な一杯は記憶からは消去され、もはや心ここにあらずという雰囲気で、そそくさとつぶやくのが、例えば次の一言。
「冷え方が最高、」
「手は口ほどに…」
次は料理です。
ここは居酒屋ですので、豪勢な凝った料理とは相容れませんが、その店自慢の名物料理やオリジナルのとても美味しそうな一品に加えて、その地域の日常的な食材、例えば港町の新鮮な魚介類や下関のフグなどがメニューに並ぶことがあります。
もちろん、TVの紹介番組ですから、好意的なコメントが大前提で、特に初めて取材に来たお店などの場合には、料理を出した店側も緊張していますので、どうしてもリップサービスが必要になります。しかも、店主に向かって、ていねいな賛辞が繰り返されているようです。
しかしここで、本当に美味しいものが出てきた時、口にした料理が想像をこえた食感を示した時などに、ここで太田さんには、やおらぎゅっと握った手を口元に持っていくクセがあるようです。またもや時間は止まり、今までのやり取りとはうってかわって、この時にはすでに店主のことなど忘れて、その視線は自らの前頭葉のあたりを内側からまさぐっているのが解かるようです。
なんとも正直な方で、後にも述べますが、特に「手が口ほどに」モノを言う、手を見れば真意が垣間見える方です。
さて、これはオプションですが、取材はどうやら店を貸し切りにはしない方針らしく、いつもの酔客たちと同席になっていることがあります。ここで、隣の酔客に話題をふられたり、せっかく○○まで来たのにどこにでもあるような一品を勧められて注文せざるをえなくなったりした時に、その背中にトホホ感が垣間見られたりするのも、まさにこの番組の予期せぬ見どころです。
暖簾と後ろ髪
お酒と食べ物の紹介が終わると、店を出て、今回の締めくくりとして暖簾の前でお店を総括します。
しかし、何といっても対象は居酒屋です。どんなにいい店でも、「美味しんぼ」風の語彙のバリエーションは不自然です。「賛辞の宝石箱」とは相容れない対象なのです。
しかも、太田さんももう店で飲まされてしまって、ましてや二軒目の取材だったりすれば、赤ら顔になってすっかり上機嫌です。
ここで、正直な太田さんが多用する言葉が、「素晴らしい」なのです。
しかも、多用するが故にはさまざまなバリエーションが必要となり、「○○は素晴らしい」「とても素晴らしい」「あれは素晴らしかった」「素晴らしいものがありましたね(虚空をみてしみじみ)」など、数々の微妙な変化球が繰り出されます。
しかし太田さん、実はここでも手が口以上にモノを言うのです。
本当に嬉しかった店での最高の大技があり、それは背景にある暖簾をやおら両手で引っ張り始め、「素晴らしいぞ、○○(店名)、また来るぞ!」
このようないくつかの見せ場を経て、太田さんは夜の街に吸い込まれるように消えていく、カメラもまるで酔眼のようにアウトフォーカスして、番組は終了するのでした。
それでは、また、YouTubeの長岡篇
長岡篇1
長岡篇2
ね、いろいろやってますでしょう?
不思議な臨場感
というわけで、これは「誰でも日常的に気軽に入れて、親しまれてきた居酒屋を紹介する」というとても良い番組です。
全国各地の良い居酒屋を知り、疑似体験できるというだけではなく、その場でなんとなく代わりばえのしない話でもしながら、太田さんと実際に呑んでいるような不思議な感覚にもなる、予期せぬ楽しさがあったとても良い番組です。
しかし、いくつかの疑問点は残ります。
日本三大居酒屋?
まずかなりいろいろな店で、「この店は本当に良い店でした。私の日本三大居酒屋が確実にまた一つ増えました。」みたいなことを真顔で言っているのですが、果たして「日本三大居酒屋」は全国にいくつあるのか??
居酒屋の名店?
また、だれでも日常的に通える、安くて気の置けない良い店を紹介するはずなのに、時々予約が必要な店で、一品数千円の料理と一杯数千円の大吟醸なんかも紹介している。こういう名店もいいけど、気張った高い店には誰もが日常的にはいけないよなあ、などとも思うのです。
日本タダ酒紀行
しかし、太田さん、すでにこの業界では名実ともに第一人者のようですので、地方に行けば、なじみの有名店に招かれて、成り行き上ついゴチになっったままそれが取材になってしまうこともあるはずです。
考えてみれば「日本居酒屋紀行」。日本の風土を考えれば、おそらくその取材の多くは「日本タダ酒紀行」でもあったはずで、そういう意味でもなんともうらやましい番組でもあるのでした。
そして、タレントでもない、料理研究科でもない、文筆家でもない太田さんそのものが、衒いの全く感じられない、基本のしっかりした文章や映像を残す。そういう意味でも、これは一つの文化なのだなあとも思うのでした。
「居酒屋研究会」、私も会員になりたいくらい。
(*なお画像は、「日本三大居酒屋」の一つ、大阪阿倍野の名店「明治屋」。となりに座ったおっちゃんの話が、大爆笑でした。)
旅チャンネルというところで放映していて、テレビ東京系でも流しているようなのですが、ヒゲのおじさんが各地の居酒屋で酒を飲んでいる所を放映するという、さすがに最初はちょっと戸惑う番組です。
この番組、実は「日本居酒屋紀行」を受けてもう10年以上も続く名企画で、最初は居酒屋でよく見かけるような酒呑みかとも思われたこのおじさんも、太田和彦さんという、後に述べますがなかなかの人物なのです。
本来は、日本全国、津々浦々の優れた居酒屋を訪問するという企画で、最初にこの番組を見た時は、確か東京の下町の飲み屋だったのですが、それはありがちな飲み屋で、そこでおじさんが飲み食いをして、夜の街に紛れ込むように去って行くという、正直なところ???な印象をどうにもできない番組だったのでした。
太田和彦さん
この番組の案内役で、企画者でもあるひげのおじさんは、太田和彦さんという本来はグラフィックデザイナーで、ネットの経歴では北京生まれ。当初は資生堂に入社して腕をふるっていたようです。最初は見知らぬ酒呑みのおじさんだったのですが、「居酒屋研究会」というものも主宰しているらしく、実はあの新潮文庫に居酒屋関連の著書が5本もあったのです。
そこで、そのうちの「超・居酒屋入門」を読んでみると、これがまたいいのです。文章に骨があって、なんともいえない味があって、しかも衒ったところのない文章は、かつて新潮文庫で野田知祐を初めて読んだ時の記憶をうっすらと思い出させるものがありました。
この本によれば、居酒屋とは「居心地を愉しむ」ところであり、街中で提供されるプライベートな空間、それは例えばヨーロッパのカフェやバールのような、気軽に入れて干渉されない場所なのですが、それが日本では居酒屋なのだということのようです。そこで、日本の中高年が、職場からも家庭からも距離を置いて、一人の個人に立ち帰る、そんな場所なのだということのようなのです。
まあ、日本では、近所のおじさんがいつでもぶらりと入って居座れるほど、喫茶店の文化が根付かなかったし、それに薄くて高いコーヒーなんか飲むなら、おいしい肴で酒でも飲みましょうということなのでしょう。
地域に根付いた名店
さて、そういう予備知識をもってこの番組を見直すと、実はなかなか味のある番組です。
まず、登場する居酒屋がとても貴重な店だったりします。
例えば、釧路の歴史のある炉端焼き屋さんなどは、建物そのものが持つ燻し銀の迫力に鬼気迫るものすらあるのですが、その炉端で、店を守り続けてきた老婆がいそいそと立働く姿。そして別の店では、既にすっかりモノトーンとなってしまった店内で、物静かな割烹着の女将さんがカウンターの片隅で手を休めてくつろぐ時、それがまるで夢二の構図そのもののようなものになっている時の、眩暈がしそうなアナクロニズム。これなんかは、すでに記録映像です。
料亭などのように決してお金をかけたわけではない建物が、まさに地元に親しまれたが故に歴史とともに受け継がれてきた、そんな味のある店。しかもなかなか行く機会のない地方の、知らなければなかなかブラリとは入りにくいお店が、映像としてたくさん残されています。
たとえば、まずYouTubeにある「会津若松篇」です。
会津若松篇1
会津若松篇2
会津若松篇3
主題と変奏
さりとて、これは居酒屋の紹介番組です。薀蓄のある厳選された食材を使って名料理人が華麗な腕をふるう、そんな見せ場はありえません。また名物店主の華麗なトークも期待できませんし、むしろこれは番組の空気をぶち壊すリスクの方が高いでしょう。
すると、番組の構成としては、注文して、呑んで、食べるだけという単調なものとならざるをえず、実際に過去の映像を見ても、このスタイルは本人も言っているように「10年前から代りばえのしない、いやまったく同じことをやっていると言ってもいい」ものになっているのです。
しかし、何回か放送を見ていると、そこにはある種の様式美としてのいくつかの見せ場があり、さらにそこにはいくつかのバリエーションがあることに気付きます。
「冷え方が最高!」
この番組では、何といってもまず一杯、何かで咽喉を潤してから料理を注文するというのがスタイルのようです。太田さんもかなりのビール党であるらしく、最初はビールから始まるパターンが多いようです。
そこでテーブルに届けられた生ビールのジョッキに手を伸ばし、最初の一口でそのままジョッキの1/3から半分くらいまで飲んでしまうのですが、ここでふと、時間が止まります。
太田さんの目が一瞬虚空を泳ぎ、明らかに冥界まで往復してしまっているのがわかります。
絶妙な間をおいて目に正気を取り戻すと、一言、
「うまい。」
この番組の最初の見せ場は、まずここです。
ここで生ビールを置いていない店だった場合には、もちろん瓶ビールになります。
しかし太田さん、著書を見ると、ビールの注ぎ方・泡の分量には一家言あるらしく、そのあたりの機微を知らない他人にビールを注がれるのは、実は嫌らしい。しかし、これはTVの取材です。そんな事情を知らない女将さんとしては、最初の一杯ぐらいはしっかりお酌するのが義務です。物静かにジェントルに呑むことを身上とした太田さんとしては、たとえ内心では最初の一杯が台無しになったとしても、番組の初っ端ですから何もコメントしないわけにもいかないのでしょう。この時、生ジョッキで冥界に遊んだときとは打ってかわって、すでに今の残念な一杯は記憶からは消去され、もはや心ここにあらずという雰囲気で、そそくさとつぶやくのが、例えば次の一言。
「冷え方が最高、」
「手は口ほどに…」
次は料理です。
ここは居酒屋ですので、豪勢な凝った料理とは相容れませんが、その店自慢の名物料理やオリジナルのとても美味しそうな一品に加えて、その地域の日常的な食材、例えば港町の新鮮な魚介類や下関のフグなどがメニューに並ぶことがあります。
もちろん、TVの紹介番組ですから、好意的なコメントが大前提で、特に初めて取材に来たお店などの場合には、料理を出した店側も緊張していますので、どうしてもリップサービスが必要になります。しかも、店主に向かって、ていねいな賛辞が繰り返されているようです。
しかしここで、本当に美味しいものが出てきた時、口にした料理が想像をこえた食感を示した時などに、ここで太田さんには、やおらぎゅっと握った手を口元に持っていくクセがあるようです。またもや時間は止まり、今までのやり取りとはうってかわって、この時にはすでに店主のことなど忘れて、その視線は自らの前頭葉のあたりを内側からまさぐっているのが解かるようです。
なんとも正直な方で、後にも述べますが、特に「手が口ほどに」モノを言う、手を見れば真意が垣間見える方です。
さて、これはオプションですが、取材はどうやら店を貸し切りにはしない方針らしく、いつもの酔客たちと同席になっていることがあります。ここで、隣の酔客に話題をふられたり、せっかく○○まで来たのにどこにでもあるような一品を勧められて注文せざるをえなくなったりした時に、その背中にトホホ感が垣間見られたりするのも、まさにこの番組の予期せぬ見どころです。
暖簾と後ろ髪
お酒と食べ物の紹介が終わると、店を出て、今回の締めくくりとして暖簾の前でお店を総括します。
しかし、何といっても対象は居酒屋です。どんなにいい店でも、「美味しんぼ」風の語彙のバリエーションは不自然です。「賛辞の宝石箱」とは相容れない対象なのです。
しかも、太田さんももう店で飲まされてしまって、ましてや二軒目の取材だったりすれば、赤ら顔になってすっかり上機嫌です。
ここで、正直な太田さんが多用する言葉が、「素晴らしい」なのです。
しかも、多用するが故にはさまざまなバリエーションが必要となり、「○○は素晴らしい」「とても素晴らしい」「あれは素晴らしかった」「素晴らしいものがありましたね(虚空をみてしみじみ)」など、数々の微妙な変化球が繰り出されます。
しかし太田さん、実はここでも手が口以上にモノを言うのです。
本当に嬉しかった店での最高の大技があり、それは背景にある暖簾をやおら両手で引っ張り始め、「素晴らしいぞ、○○(店名)、また来るぞ!」
このようないくつかの見せ場を経て、太田さんは夜の街に吸い込まれるように消えていく、カメラもまるで酔眼のようにアウトフォーカスして、番組は終了するのでした。
それでは、また、YouTubeの長岡篇
長岡篇1
長岡篇2
ね、いろいろやってますでしょう?
不思議な臨場感
というわけで、これは「誰でも日常的に気軽に入れて、親しまれてきた居酒屋を紹介する」というとても良い番組です。
全国各地の良い居酒屋を知り、疑似体験できるというだけではなく、その場でなんとなく代わりばえのしない話でもしながら、太田さんと実際に呑んでいるような不思議な感覚にもなる、予期せぬ楽しさがあったとても良い番組です。
しかし、いくつかの疑問点は残ります。
日本三大居酒屋?
まずかなりいろいろな店で、「この店は本当に良い店でした。私の日本三大居酒屋が確実にまた一つ増えました。」みたいなことを真顔で言っているのですが、果たして「日本三大居酒屋」は全国にいくつあるのか??
居酒屋の名店?
また、だれでも日常的に通える、安くて気の置けない良い店を紹介するはずなのに、時々予約が必要な店で、一品数千円の料理と一杯数千円の大吟醸なんかも紹介している。こういう名店もいいけど、気張った高い店には誰もが日常的にはいけないよなあ、などとも思うのです。
日本タダ酒紀行
しかし、太田さん、すでにこの業界では名実ともに第一人者のようですので、地方に行けば、なじみの有名店に招かれて、成り行き上ついゴチになっったままそれが取材になってしまうこともあるはずです。
考えてみれば「日本居酒屋紀行」。日本の風土を考えれば、おそらくその取材の多くは「日本タダ酒紀行」でもあったはずで、そういう意味でもなんともうらやましい番組でもあるのでした。
そして、タレントでもない、料理研究科でもない、文筆家でもない太田さんそのものが、衒いの全く感じられない、基本のしっかりした文章や映像を残す。そういう意味でも、これは一つの文化なのだなあとも思うのでした。
「居酒屋研究会」、私も会員になりたいくらい。
(*なお画像は、「日本三大居酒屋」の一つ、大阪阿倍野の名店「明治屋」。となりに座ったおっちゃんの話が、大爆笑でした。)
Posted by mouf at 16:54│Comments(0)