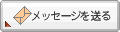2008年09月21日
停滞前線
しかし、かなりの勢いで雨が降っているのです。
台風が停滞前線を引いていて、時々雷鳴とともに激しい雨が降っています。ぐしょぬれになる覚悟が固まらず、おかげでどこにも行けず部屋に降り込められています。
台風が停滞前線を引いていて、時々雷鳴とともに激しい雨が降っています。ぐしょぬれになる覚悟が固まらず、おかげでどこにも行けず部屋に降り込められています。
しかし、こういう雨は、嫌いではないのです。平日は温度管理された職場にいることが多いため、夕立があったことすら知らずに帰宅するようなことが当たり前のようになっているので、こういう日に、隣人も外出してテレビの音もない自分の部屋の中で、ひたすらに雨の音を聞く、そして激しい雨の中を通りすぎる車の音を聞く、こういうのもとても好きです。また、このくらいの雨の日に、やむを得ず車に乗ることも好きで、全開にしたワイパーの中に、一コマずつ変化しては洗い流されていくような雨と街が作り出す光景など、心躍るものがあります。
さて、最近考えることはといえば、書くことと打つことの違いなどなど。
たとえば外国語を使うときなのですが、私達は外国語を覚えるときに、日本語から変換させる形で覚えていきます。まず表現したい内容を日本語で思い浮かべ、そこで必要な単語を外国後に置き換えて、文法に合わせて並べ替え調整する。これは暗号文を作るときのパターンですね。するとこれが、その言葉を母国語にする人々にとっては、間違っていなくてもとても不自然に感じられます。つまり、外国語としての表現は、表現したい内容に必要な単語や文法を取り付けていく、ロボットの組み立てみたいなものなのですが、これに対して母国語は、年月を掛けて状況に応じた表現の工夫を行った結果、いわば生き物のようにして育った言葉だからです。そのなかで、おかしな表現は淘汰されて、背景には意味の正誤だけではなく、必ずある種の「言葉の感覚」があります。
だから、言葉は暗号ではなく、その人の生活の中で組み立てられた「生き物」なので、ある状況の中で、ある人が表現したい心情から生まれる表現は、原則として一つです。
ここで、書くという行為にも同じような側面があって、ある人がなにかを表現するために書きつつある文章では、原則としてその人間が次に書き連ねるべき言葉も一つです。それは、言葉が人間の心情を置換するための記号ではなく、書くことによって漠然とした心的状況に形を与えていく側面がむしろ大事だからだと思います。だから、書くことによって、漠然とした思惟に形を与え育てていく、それが書くことなのだと思います。
日本語で書くという行為の中で、従来鬱陶しかったステップといえば、頭の中に文章があるにもかかわらず、それを画数の多い漢字として筆記する部分でした。漢字にしているうちに、文章の流れが分断されてしまう。そこで例えば、ヘミングウェイが立ったままタイピングしているなどという話を聞くと、単純な26文字の文化に憧れなども感じるし、また考えた内容がダイレクトに文字になるというブルトンの「自動筆記」などを読むと、思考が簡単に文字に置き換えられることに、ある種の「自由さ」も感じるのでした。
さて、文章入力技術の進歩によって日本語を「打つ」ようになって、実は今さらながら、どんどんイメージとは違う展開になっています。もちろん、入力のスピードがかなり改善し、まあ「自動筆記」に近い状況なのですが…
それでもやはりいくつかの障碍となる小さなステップはあります。たとえば、やはり漢字の入力。時に変換候補を延々と探さなければいけない状況などですね。それからもう一つは、誤変換。しかし、一番気になるのは、文字を打っていながら、頭の中で別の表現を考える余裕ができるため、その文章の流れが終わらないうちに文章を変えたくなってしまう。これは修正技術が簡単であるための副産物でもあります。つまりは、表現が文章として育つことを待たず、中途でどんどん部品が置き換えられてしまって、ギクシャクしたロボットのような文章になってしまう。これは「コピペの弊害」です。
そこには、背景に外国語の異なった構造体系の知識や感覚、また文章は論理的に簡潔でなければなららないなどというお仕着せもありそうです。
しかし、これはたしか河野多恵子ですが、日本語は書かれるという形で長い年月を掛けて出来上がってきたのだから、書くという行為から急に離れることはできないというようなことを書いていました。少なくとも、文章には読まれるのに最適なスピードがあるように、日本語を想念から文字にするにあたっても、適したスピードというものがあり、そのスピードは「書くという行為」のなかで出来上がってきた日本語の構造の一部そのものなのでしょう。
だから、日本語をいくら打ってもあまり楽しくないし、どこかギクシャクしてしまう。
しかしこれからは、最初から「日本語を打つ」ことに適応した世代が主役となるのでしょう。
おっ、雨やんでる♪
さて、最近考えることはといえば、書くことと打つことの違いなどなど。
たとえば外国語を使うときなのですが、私達は外国語を覚えるときに、日本語から変換させる形で覚えていきます。まず表現したい内容を日本語で思い浮かべ、そこで必要な単語を外国後に置き換えて、文法に合わせて並べ替え調整する。これは暗号文を作るときのパターンですね。するとこれが、その言葉を母国語にする人々にとっては、間違っていなくてもとても不自然に感じられます。つまり、外国語としての表現は、表現したい内容に必要な単語や文法を取り付けていく、ロボットの組み立てみたいなものなのですが、これに対して母国語は、年月を掛けて状況に応じた表現の工夫を行った結果、いわば生き物のようにして育った言葉だからです。そのなかで、おかしな表現は淘汰されて、背景には意味の正誤だけではなく、必ずある種の「言葉の感覚」があります。
だから、言葉は暗号ではなく、その人の生活の中で組み立てられた「生き物」なので、ある状況の中で、ある人が表現したい心情から生まれる表現は、原則として一つです。
ここで、書くという行為にも同じような側面があって、ある人がなにかを表現するために書きつつある文章では、原則としてその人間が次に書き連ねるべき言葉も一つです。それは、言葉が人間の心情を置換するための記号ではなく、書くことによって漠然とした心的状況に形を与えていく側面がむしろ大事だからだと思います。だから、書くことによって、漠然とした思惟に形を与え育てていく、それが書くことなのだと思います。
日本語で書くという行為の中で、従来鬱陶しかったステップといえば、頭の中に文章があるにもかかわらず、それを画数の多い漢字として筆記する部分でした。漢字にしているうちに、文章の流れが分断されてしまう。そこで例えば、ヘミングウェイが立ったままタイピングしているなどという話を聞くと、単純な26文字の文化に憧れなども感じるし、また考えた内容がダイレクトに文字になるというブルトンの「自動筆記」などを読むと、思考が簡単に文字に置き換えられることに、ある種の「自由さ」も感じるのでした。
さて、文章入力技術の進歩によって日本語を「打つ」ようになって、実は今さらながら、どんどんイメージとは違う展開になっています。もちろん、入力のスピードがかなり改善し、まあ「自動筆記」に近い状況なのですが…
それでもやはりいくつかの障碍となる小さなステップはあります。たとえば、やはり漢字の入力。時に変換候補を延々と探さなければいけない状況などですね。それからもう一つは、誤変換。しかし、一番気になるのは、文字を打っていながら、頭の中で別の表現を考える余裕ができるため、その文章の流れが終わらないうちに文章を変えたくなってしまう。これは修正技術が簡単であるための副産物でもあります。つまりは、表現が文章として育つことを待たず、中途でどんどん部品が置き換えられてしまって、ギクシャクしたロボットのような文章になってしまう。これは「コピペの弊害」です。
そこには、背景に外国語の異なった構造体系の知識や感覚、また文章は論理的に簡潔でなければなららないなどというお仕着せもありそうです。
しかし、これはたしか河野多恵子ですが、日本語は書かれるという形で長い年月を掛けて出来上がってきたのだから、書くという行為から急に離れることはできないというようなことを書いていました。少なくとも、文章には読まれるのに最適なスピードがあるように、日本語を想念から文字にするにあたっても、適したスピードというものがあり、そのスピードは「書くという行為」のなかで出来上がってきた日本語の構造の一部そのものなのでしょう。
だから、日本語をいくら打ってもあまり楽しくないし、どこかギクシャクしてしまう。
しかしこれからは、最初から「日本語を打つ」ことに適応した世代が主役となるのでしょう。
おっ、雨やんでる♪
Posted by mouf at 16:57│Comments(0)