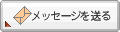2008年11月04日
一次元に萌えたりし消息
さて、またもや三連休。
果たして、今回こそ香川に讃岐うどん行脚に行ったか? といえば…
行きませんでした。
このあたりの経緯に関しましては、また後日。
果たして、今回こそ香川に讃岐うどん行脚に行ったか? といえば…
行きませんでした。
このあたりの経緯に関しましては、また後日。
それでは、この連休は何をしていたのかといえば…
そもそもは、先週から読んでいた「幸福な生活について」。
これがまたいいのです。
作者は、ネロ帝の家庭教師も務めた賢人で、しかもそのネロ帝から死を命じられた、ある意味常人では勉められない生涯を送った方です。だいたい、法と社会と技術に守られている現在の日本人に比べれば、当時の生き方はさぞかし過酷だったはずなのですが、そんな世の中に生まれて、そこでいかに幸福に生きるか、という話を、こういう生涯を送った張本人が理路整然と説くのです。鬼気迫るものがあります。
やっぱり、西洋の心根にある土台骨の太さは、2000年前からごっついものがありました。
そこで、実は以前にも少し書きましたが、某端末を所有しています。
この某端末、オプションでいろいろなアプリケーションを導入することができまして、数百円の追加投資で、この小さな一台が高性能の電卓になったり、優秀な辞書にもなります。
この週末は、Stanzaというものを入れてみたのです。これは無料のテキストリーダーで、これで何ができるかといえば、つまりは青空文庫やProj. Gutenbergなどの電子図書館の本が読めるのです。つまりは、そこに収録された古典が、ほぼ無料で入手できて、さらにはこの小さな端末に無尽蔵に携帯できるのです。
もちろん今までも、似たようなことはPDAやPSPで十分にできました。しかし、そこで問題だったのは、インターフェイスの質感です。PCで文章を読むと、どうにもそこに越えがたい違和感が残ってしまう人は多いと思うのですが、小型端末でもそれを両手で持って、ボタンでページをめくりながらディスプレイを見る、ここでもどこかでしっくり行かないければ、その機能はもうそのまま放置だったのです。
ところが、某端末とStanza、意外といいのです。文庫本より小さく、片手で操作ができて、しかも画面の配列もいい塩梅。寝転がって読めるし、夕方暗くなっても端末画面ほのかに発光するので、きちんと読めてしまいます。
ありゃ、意外といいじゃん、
とのことでまずは泉鏡花の「黒百合」。
これは、恐ろしい作品で、旧かなの漢字とルビの羅列です。そしてそれに脳が麻痺し始めると、そこからはまるで麻薬のように読者を引き込みます。
しかし、麻痺できるまでの最初の数ページに脳が辛抱できなければ、難解な挫折体験として記憶されるに留まってしまうのです。
久しぶりの鏡花、果たして某端末の縦書きで行けるか?
はぁ… 堪能してしまいました…
というわけで、引き続き、「高野聖」。
これなんて、もうあらすじもしっかり解かっているのに、読み返せば意外と深い。
足元を掬われたかの如く暫し茫然とすること一度ならず、また明治の鏡花の繰り拡げる女性の色香の描写が、凄まじいのです。これまた無事に一気に読了。
こうなれば、やはり「草枕」。
これは、まあ春の温泉旅行みたいな気楽な雰囲気を基調にしているので、いろいろ考えさせられながらも呑気に読めます。
やっぱり、旅先でイワクありげな一筋ではない女性(にょしょう)が出てきて、油断すると頭からバリバリ食われてしまいそうになるのが、怖いというか、それでも食われてみたいとも言うか、こういう筋書きも基本的にいいものです。
すると、幸田露伴ではとりあえず「蒲生氏郷」を保存しておいて、まだ読んだことのなかった「平将門」。露伴のおじさん、さすがに京大教授になっただけのことはあります。綿密でしかもお酒がらみのちょっとした描写がとてもいい。
そして、中島敦の「悟浄歎異」。
これは、不思議と上記のセネカつながりなところもある作品で、何度読み直してもやっぱりいい。
で、先ほど読み終わったのが、「杜子春」。
蛾眉山の仙人の最後の質問には、我が事としてしばらく真面目に考えさせられましたよ。そこで芥川が杜子春に言わせたあの科白、もうすっかりやられました。
ということで、陶酔の三日間だったのです。もう頭の中は漢字だらけになっていて、やっぱり明治の人達は深い、深い。得るトコロもありました。
あとは、デカルトやデュマやフローベールなんかも保存したのですが、さすがにこれは寝転がっては読めず。しかし、あのサイズでこれだけの作品がシレっと保存できる某端末、なかなかやります。
そもそもは、先週から読んでいた「幸福な生活について」。
これがまたいいのです。
作者は、ネロ帝の家庭教師も務めた賢人で、しかもそのネロ帝から死を命じられた、ある意味常人では勉められない生涯を送った方です。だいたい、法と社会と技術に守られている現在の日本人に比べれば、当時の生き方はさぞかし過酷だったはずなのですが、そんな世の中に生まれて、そこでいかに幸福に生きるか、という話を、こういう生涯を送った張本人が理路整然と説くのです。鬼気迫るものがあります。
やっぱり、西洋の心根にある土台骨の太さは、2000年前からごっついものがありました。
そこで、実は以前にも少し書きましたが、某端末を所有しています。
この某端末、オプションでいろいろなアプリケーションを導入することができまして、数百円の追加投資で、この小さな一台が高性能の電卓になったり、優秀な辞書にもなります。
この週末は、Stanzaというものを入れてみたのです。これは無料のテキストリーダーで、これで何ができるかといえば、つまりは青空文庫やProj. Gutenbergなどの電子図書館の本が読めるのです。つまりは、そこに収録された古典が、ほぼ無料で入手できて、さらにはこの小さな端末に無尽蔵に携帯できるのです。
もちろん今までも、似たようなことはPDAやPSPで十分にできました。しかし、そこで問題だったのは、インターフェイスの質感です。PCで文章を読むと、どうにもそこに越えがたい違和感が残ってしまう人は多いと思うのですが、小型端末でもそれを両手で持って、ボタンでページをめくりながらディスプレイを見る、ここでもどこかでしっくり行かないければ、その機能はもうそのまま放置だったのです。
ところが、某端末とStanza、意外といいのです。文庫本より小さく、片手で操作ができて、しかも画面の配列もいい塩梅。寝転がって読めるし、夕方暗くなっても端末画面ほのかに発光するので、きちんと読めてしまいます。
ありゃ、意外といいじゃん、
とのことでまずは泉鏡花の「黒百合」。
これは、恐ろしい作品で、旧かなの漢字とルビの羅列です。そしてそれに脳が麻痺し始めると、そこからはまるで麻薬のように読者を引き込みます。
しかし、麻痺できるまでの最初の数ページに脳が辛抱できなければ、難解な挫折体験として記憶されるに留まってしまうのです。
久しぶりの鏡花、果たして某端末の縦書きで行けるか?
はぁ… 堪能してしまいました…
というわけで、引き続き、「高野聖」。
これなんて、もうあらすじもしっかり解かっているのに、読み返せば意外と深い。
足元を掬われたかの如く暫し茫然とすること一度ならず、また明治の鏡花の繰り拡げる女性の色香の描写が、凄まじいのです。これまた無事に一気に読了。
こうなれば、やはり「草枕」。
これは、まあ春の温泉旅行みたいな気楽な雰囲気を基調にしているので、いろいろ考えさせられながらも呑気に読めます。
やっぱり、旅先でイワクありげな一筋ではない女性(にょしょう)が出てきて、油断すると頭からバリバリ食われてしまいそうになるのが、怖いというか、それでも食われてみたいとも言うか、こういう筋書きも基本的にいいものです。
すると、幸田露伴ではとりあえず「蒲生氏郷」を保存しておいて、まだ読んだことのなかった「平将門」。露伴のおじさん、さすがに京大教授になっただけのことはあります。綿密でしかもお酒がらみのちょっとした描写がとてもいい。
そして、中島敦の「悟浄歎異」。
これは、不思議と上記のセネカつながりなところもある作品で、何度読み直してもやっぱりいい。
で、先ほど読み終わったのが、「杜子春」。
蛾眉山の仙人の最後の質問には、我が事としてしばらく真面目に考えさせられましたよ。そこで芥川が杜子春に言わせたあの科白、もうすっかりやられました。
ということで、陶酔の三日間だったのです。もう頭の中は漢字だらけになっていて、やっぱり明治の人達は深い、深い。得るトコロもありました。
あとは、デカルトやデュマやフローベールなんかも保存したのですが、さすがにこれは寝転がっては読めず。しかし、あのサイズでこれだけの作品がシレっと保存できる某端末、なかなかやります。
Posted by mouf at 02:46│Comments(0)