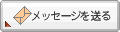2007年01月14日
切手なの?
いやいや、とうとう鶏のホロコーストが始まっちゃいましたね。
こういうのを見ると、「人間に食われる」という、100%相手のご都合の目的のために生まれ・生かされてきた動物が、その唯一の存在意義すらも奪われてあっけなく殺されていくわけで、かなり複雑な気持ちになるんですよね。
こういうのを見ると、「人間に食われる」という、100%相手のご都合の目的のために生まれ・生かされてきた動物が、その唯一の存在意義すらも奪われてあっけなく殺されていくわけで、かなり複雑な気持ちになるんですよね。
養鶏業者の人達もかわいそうですけど、もちろん鶏もかわいそう。(合掌)
人類って、どこか勘違いしてますよね、今。きっとろくな滅び方しませんよね。
もしも逃亡に成功して、生き延びることができた鶏達がいたら、是非ともこの悲劇を後の世まで語り継いで、「アンネの日記」みたいなのとか、「人生は美しい」みたいな映画なんかも製作して欲しいものです。
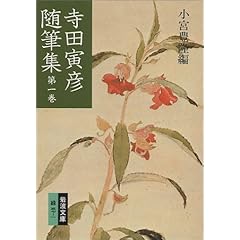
さて今朝ほど、寝起きに布団のなかでぼんやりしながら、枕元にたまたまあった本を読んでいたのです。これって、明治時代の人が書いた本で、その中に当時の日本橋界隈、三越百貨店があってその向かいに丸善があった(裏には魚河岸もあった?)、などという様子がいろいろ詳しく書いてあるのです。
そこで、ふと目を引く一文があって、当時の三越の玄関を入ると、
ね、なんか変でしょう?
そこで、この「切手」っていう言葉、そういえば以前からどこか引っかかっていたのですよ。
というのも、そもそもは手紙にはる「切手」と「小切手」の関係です。
「切手」の方は自分たちにもものすごくなじみがあって、街にでればコンビニやタバコ屋でも買える純粋に庶民的なもの。ところが、「小切手」の方は「小」のくせに、実は庶民には使ったことがある人なんかあまりいない、「お金持ち」のアイテムなのですよね。
何ゆえに、こっちが「小」切手なんだろ?
おそらく、日本の郵便システムが整備されたのは明治時代なので、切手も小切手もそれまでの欧米の仕組みを取り入れたものだと思われるのですが…
そこで、Wikipediaをみてみると、小切手の歴史はかなり古く、3世紀のペルシャですでに手紙による信用換金が始まっていて、9世紀にはアラブ人が中国で小切手を使っていたらしい。でも、これをみても小切手は原則としてchequeだし、切手はstampとかtimbleとかいう、生い立ちも単語の字ズラもぜんぜん違う言葉なんですよね。
小切手を「小」にしたのは、どうやら日本の社会の仕組みだったのでしょうか?
そこで、「切手」のWikipediaをみてみると…
なるほど、すると冒頭の文章も、「切手」を「商品券」と置き換えれば確かにすんなりと意味が通ります!
もともとあった「切手」の言葉を使って、明治の郵便制度の整備のときに「郵便切手」という言葉を作ったわけですね。そのうちに、皆さんにいちばんなじみがあったのが「郵便切手」なので、これを短く「切手」と呼ぶようになって、それ以外は「商品券」などと呼び分けるようになったのでしょうか。
たしかに、贈答品として高額の「郵便切手」を送られても、使い道に困ってアリガタ迷惑だし、きっと無駄になりそうです。
しかし、それではなぜ「小切手」は「小」なんだ??
しょうがないので、Wikipediaの「小切手」をみると…
へぇ、小切手って「小切手法」に定められた正式な法廷用語なんだ...(「小」なのに)
しかも、この小切手法、制定されたのが昭和8年?
日本って、昭和8年まで小切手使わずに、外国と取引してたのか??
日本が邪馬台国だった頃から諸外国では使われていた「小切手」。「切手=商品券」ですら江戸時代よりも前から使われていて、郵便切手ですら明治から使われていたというのに、「小切手」の公式デビューは予想外に歴史が浅く、昭和に入ってからだったのですね。
すると、むむ?
実は「小」は、「小さい」ではなく、「Jr.」だったのでしょうか?
いますよね、「小カトー」とか「小ピピン」とか、先祖よりも偉大だった「小」な人達。
なるほど、「小切手」は「切手ぐゎ」ではなく「切手Jr.」だったのか!
お役所のネーミングにしては、なかなかクールで奥が深かったわけですねぇ(?)。
などといいつつ、長閑な休日は終わろうとしているようです…
*あ、それからこの間新宿の文房具屋で、Targaの新しいシリーズを販売していました。(赤とか緑とかのカラフルなシリーズで、3万円ぐらい)
人類って、どこか勘違いしてますよね、今。きっとろくな滅び方しませんよね。
もしも逃亡に成功して、生き延びることができた鶏達がいたら、是非ともこの悲劇を後の世まで語り継いで、「アンネの日記」みたいなのとか、「人生は美しい」みたいな映画なんかも製作して欲しいものです。
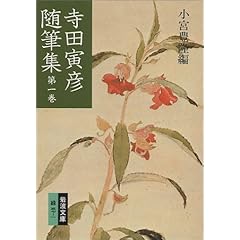
さて今朝ほど、寝起きに布団のなかでぼんやりしながら、枕元にたまたまあった本を読んでいたのです。これって、明治時代の人が書いた本で、その中に当時の日本橋界隈、三越百貨店があってその向かいに丸善があった(裏には魚河岸もあった?)、などという様子がいろいろ詳しく書いてあるのです。
そこで、ふと目を引く一文があって、当時の三越の玄関を入ると、
正面の階段の入り口の左側に商品切手を売る所がある。ここはいつでも人が込み合っていて、数百円のを持っていく人もあれば数十円のを数十枚買っていく人もある。そうかと思うと一円のを一枚いばって買っていく人もある。ともかくもここには人間の好意が不思議な天秤にかけられて、まず金に換算され、次に切手に両替えされる、現代の文化が発明した最も巧妙な機関がすえらえてある。
ね、なんか変でしょう?
そこで、この「切手」っていう言葉、そういえば以前からどこか引っかかっていたのですよ。
というのも、そもそもは手紙にはる「切手」と「小切手」の関係です。
「切手」の方は自分たちにもものすごくなじみがあって、街にでればコンビニやタバコ屋でも買える純粋に庶民的なもの。ところが、「小切手」の方は「小」のくせに、実は庶民には使ったことがある人なんかあまりいない、「お金持ち」のアイテムなのですよね。
何ゆえに、こっちが「小」切手なんだろ?
おそらく、日本の郵便システムが整備されたのは明治時代なので、切手も小切手もそれまでの欧米の仕組みを取り入れたものだと思われるのですが…
そこで、Wikipediaをみてみると、小切手の歴史はかなり古く、3世紀のペルシャですでに手紙による信用換金が始まっていて、9世紀にはアラブ人が中国で小切手を使っていたらしい。でも、これをみても小切手は原則としてchequeだし、切手はstampとかtimbleとかいう、生い立ちも単語の字ズラもぜんぜん違う言葉なんですよね。
小切手を「小」にしたのは、どうやら日本の社会の仕組みだったのでしょうか?
そこで、「切手」のWikipediaをみてみると…
切手の日本語はもともとは持参人に表示された商品を引き渡す一種の商品券を意味するもので、当初は「切符手形」と称していたが、その後略されて切手とされるようになった。
なるほど、すると冒頭の文章も、「切手」を「商品券」と置き換えれば確かにすんなりと意味が通ります!
もともとあった「切手」の言葉を使って、明治の郵便制度の整備のときに「郵便切手」という言葉を作ったわけですね。そのうちに、皆さんにいちばんなじみがあったのが「郵便切手」なので、これを短く「切手」と呼ぶようになって、それ以外は「商品券」などと呼び分けるようになったのでしょうか。
たしかに、贈答品として高額の「郵便切手」を送られても、使い道に困ってアリガタ迷惑だし、きっと無駄になりそうです。
しかし、それではなぜ「小切手」は「小」なんだ??
しょうがないので、Wikipediaの「小切手」をみると…
へぇ、小切手って「小切手法」に定められた正式な法廷用語なんだ...(「小」なのに)
しかも、この小切手法、制定されたのが昭和8年?
日本って、昭和8年まで小切手使わずに、外国と取引してたのか??
日本が邪馬台国だった頃から諸外国では使われていた「小切手」。「切手=商品券」ですら江戸時代よりも前から使われていて、郵便切手ですら明治から使われていたというのに、「小切手」の公式デビューは予想外に歴史が浅く、昭和に入ってからだったのですね。
すると、むむ?
実は「小」は、「小さい」ではなく、「Jr.」だったのでしょうか?
いますよね、「小カトー」とか「小ピピン」とか、先祖よりも偉大だった「小」な人達。
なるほど、「小切手」は「切手ぐゎ」ではなく「切手Jr.」だったのか!
お役所のネーミングにしては、なかなかクールで奥が深かったわけですねぇ(?)。
などといいつつ、長閑な休日は終わろうとしているようです…
*あ、それからこの間新宿の文房具屋で、Targaの新しいシリーズを販売していました。(赤とか緑とかのカラフルなシリーズで、3万円ぐらい)
Posted by mouf at 17:49│Comments(0)
│文庫