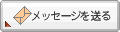2005年06月05日
黒の過程
「黒の過程」って御存じです?
(以下、長くてスカしているので、興味のない人はスルーしてください。)
(以下、長くてスカしているので、興味のない人はスルーしてください。)
マルグリット・ユルスナールという人が書いたお話です。
舞台は16世紀、宗教紛争が猛威を揮っていたフランス。16世紀といえばルネサンスの初期で、冒頭の序文にはピコ・デ・ラ・ミランドラの文章がそのまま掲げられていて、これがこの作品全体のテーマにもなっています。カトリーヌ・ド・メディシスやエチエンヌ・ドレ、ヴェザリウスは実名で登場しますし、背景にはダビンチやモンテーニュなどの作品の薀蓄も盛り込まれています。
主人公はこの激動の時代の人物で、表向きは医師でありながら、錬金術と哲学にも通じ、彼の著作は危険思想とみなされて発禁処分を受け、そのために追われ、偽名の医師として各地を転々としています。
この主人公が非常に理知的。誰もが常識として考えようともしないこと、そして世間の流れに乗って無自覚に対処していることなどを敏感に感じ取り、限界まで突きつめて考えている。そして考えることのできない「微妙なもの」(=非常に危険だったもの)については、結論を出さずにそのまま置いておく(語りえないことは沈黙っすね)。この主人公の内面の理知的な述懐が、実はこのお話のメインになっていて、これがまたとてもいいんです。
例えば、
また例えば、
そして、20歳の時の主人公が、世の中の動乱をみて軍人になろうとしていた友人につぶやく言葉。
こういうのを読むと、頭をがつんと殴られたような気がするんですよね、単純だから。
人間には、どうにもやる気が出ない状況ってのがあります。
ひとつは、それをやらずに避けて通ることができないはずなのに、自分ではそれをやることに興味も本質的な意味も見出せないとき。
そして、それをやることによって、善くも悪しくも自らの未来が限定されてしまうとき。
しかし、それはいずれも他人の敷いた道をたどって生きていく場合。そこから先に広がるのは、金儲けと勢力争いと繁殖のための目くるめく「茎の世界」です。
主人公は錬金術師ですが、瞬時に全てを悟って人体錬成とかやっていたわけではありません。
当時の錬金術というのは「化学」の前身で、「黒の過程」とは、化金石を実現するのにもっとも困難とされたいわば秘伝の過程だったようです。
しかし、長い「黒い過程」を歩きながらも、最終的に主人公は「人間」として死ぬことを選択します。
この世界を生きていくにあたって、美しい理想郷はないでしょう。
世界のみえなくてもいい部分が見えてしまう人間、そしてそれを自分にごまかせない人間は、それがイヤなら、たぶん長い「黒の過程」を歩かなければならない。なぜなら自分達が嫌っているものそのものが「黒」だからだと思うのです。そして、ここで立ち止まることは、「黒の世界」に飲み込まれていくだけのような…
こんなんでいかがでしょう。
あ、これです。
ユルスナール・セレクション 2 黒の過程
(しかし、これはお薦めしませんし、紀伊国屋とかに行かないと見つからないわな、きっと。)
舞台は16世紀、宗教紛争が猛威を揮っていたフランス。16世紀といえばルネサンスの初期で、冒頭の序文にはピコ・デ・ラ・ミランドラの文章がそのまま掲げられていて、これがこの作品全体のテーマにもなっています。カトリーヌ・ド・メディシスやエチエンヌ・ドレ、ヴェザリウスは実名で登場しますし、背景にはダビンチやモンテーニュなどの作品の薀蓄も盛り込まれています。
主人公はこの激動の時代の人物で、表向きは医師でありながら、錬金術と哲学にも通じ、彼の著作は危険思想とみなされて発禁処分を受け、そのために追われ、偽名の医師として各地を転々としています。
この主人公が非常に理知的。誰もが常識として考えようともしないこと、そして世間の流れに乗って無自覚に対処していることなどを敏感に感じ取り、限界まで突きつめて考えている。そして考えることのできない「微妙なもの」(=非常に危険だったもの)については、結論を出さずにそのまま置いておく(語りえないことは沈黙っすね)。この主人公の内面の理知的な述懐が、実はこのお話のメインになっていて、これがまたとてもいいんです。
例えば、
苦悩は、したがってまた歓喜は、それと同時に善は、それにわたしたちが悪と名づけているものは、さらに正義は、そして最後に、どんな形をとるにせよ、そういった反対物を識別するのに役立つ悟性は、血の世界とひょっとしたら樹液の世界と、稲妻にも似た網目模様を描く神経網を張りめぐらせた肉の世界と、至高善である光を目指して伸び、水の不足に苦しみ、寒さには身を縮め、他の植物の邪な侵入にたいしてはあらんかぎりの力をもって抵抗する茎の世界だけにしか存在しないことをはっきり示しているように思います。その他の世界つまり鉱物の世界と精神の世界(それが存在するとしてですが)は、もしかしたら無感覚で落ち着き払っており、私達の喜びや苦しみを越えているもの、あるいはその手前にあるものなのかもしれません。私達の苦悩はあるいは宇宙の製造所のなかで生じた微小な例外でしかありえず、そのことがまた、私たちが敬虔に神と呼んでいるあの不変不易の実体の無関心を説明するものなのかも知れません。
また例えば、
君らの言う黄金時代というやつは、ダマスカスだのコンスタンチノープルだのと同じことで、遠く離れているからこそ美しいのだ。それらの町のらい病患者やのたれ死にした犬たちを見るためには、その街路を歩いてみなければならない。君のいうプルタルコスがぼくに教えたのは、ヘファイスチオーンが、まるではじめて病気にかかった男のように、節食の日にも頑として食べ続けたこと、アレクサンドルは、ドイツの兵隊上がりの乱暴者のように暴飲したことぐらいのものだ。アダム以来、二本脚の動物で人間の名に値したものはそう多くはないのだよ。
そして、20歳の時の主人公が、世の中の動乱をみて軍人になろうとしていた友人につぶやく言葉。
プルタルコスでも読んで、栄光だの英雄だのに興奮するがいい。ぼくにとって大事なのは、人間以上のものになることだ。
こういうのを読むと、頭をがつんと殴られたような気がするんですよね、単純だから。
人間には、どうにもやる気が出ない状況ってのがあります。
ひとつは、それをやらずに避けて通ることができないはずなのに、自分ではそれをやることに興味も本質的な意味も見出せないとき。
そして、それをやることによって、善くも悪しくも自らの未来が限定されてしまうとき。
しかし、それはいずれも他人の敷いた道をたどって生きていく場合。そこから先に広がるのは、金儲けと勢力争いと繁殖のための目くるめく「茎の世界」です。
主人公は錬金術師ですが、瞬時に全てを悟って人体錬成とかやっていたわけではありません。
当時の錬金術というのは「化学」の前身で、「黒の過程」とは、化金石を実現するのにもっとも困難とされたいわば秘伝の過程だったようです。
しかし、長い「黒い過程」を歩きながらも、最終的に主人公は「人間」として死ぬことを選択します。
この世界を生きていくにあたって、美しい理想郷はないでしょう。
世界のみえなくてもいい部分が見えてしまう人間、そしてそれを自分にごまかせない人間は、それがイヤなら、たぶん長い「黒の過程」を歩かなければならない。なぜなら自分達が嫌っているものそのものが「黒」だからだと思うのです。そして、ここで立ち止まることは、「黒の世界」に飲み込まれていくだけのような…
こんなんでいかがでしょう。
あ、これです。
ユルスナール・セレクション 2 黒の過程
(しかし、これはお薦めしませんし、紀伊国屋とかに行かないと見つからないわな、きっと。)
Posted by mouf at 20:39│Comments(0)
│文庫